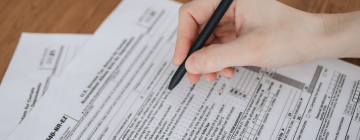成年後見制度の申立て手続き:家庭裁判所での流れを解説
高齢化が進むなか、「親が認知症になって通帳が使えない」「介護施設の契約ができない」といった相談が増えています。
このような場面で活用されるのが「成年後見制度」です。
成年後見制度は、本人の判断能力が不十分になった場合に、家庭裁判所が選任した「成年後見人」が法律面や財産面で本人をサポートする仕組みです。
本記事では、家庭裁判所への申立て手続きの流れと注意点についてわかりやすく解説します。

成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力が不十分な方のために、家庭裁判所が後見人を選任し、本人を法的に支援する制度です。
制度には3つの類型がありますが、ここでは「法定後見制度」のうち、本人の判断能力が既に低下しているケースを前提とします。
申立てを行える人は誰?
成年後見制度の申立ては、以下の人が行うことができます。
-
- 本人
- 配偶者
- 4親等内の親族(子、兄弟姉妹、甥姪など)
- 市区町村長(必要に応じて)
親族がいない場合でも、市町村が申立てを行うことができるため、独居の高齢者でも制度を利用することが可能です。

成年後見申立ての手続きの流れ
必要書類の準備
申立てには、以下のような書類が必要です:
| 必要書類 | 内容 |
| 申立書 | 家庭裁判所指定の様式あり |
| 医師の診断書 | 判断能力が低下している旨を証明 |
| 戸籍謄本 | 本人と申立人の関係を確認するため |
| 財産目録・収支予定表 | 本人の財産状況と生活費などを記載 |
| 親族関係図 | 他の相続人や親族との関係を示す図 |
※その他、通帳の写し、不動産登記簿、年金通知書などが必要な場合もあります。
家庭裁判所に申立て
必要書類をそろえたうえで、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
申立ての費用として、以下がかかります:
-
- 収入印紙(申立て1件800円程度)
- 予納郵券(裁判所により異なる)
- 医師の診断書料(10,000~30,000円程度が相場)
家庭裁判所による審理・調査
申立て後、裁判所は次のような手続きを行います:
-
- 本人との面接(本人照会):判断能力の確認
- 申立人との面談:状況の聞き取り
- 家庭裁判所調査官による調査:家庭の事情・財産状況などを確認
- 必要に応じて、親族照会も実施されます
審判と後見人の選任
裁判所の判断により、後見人が選ばれると「審判書」が送達され、正式に後見人の業務が開始されます。
※通常は、申立てから選任まで1.5〜3カ月程度かかります。
後見人の役割と義務
選任された後見人は、以下のような義務を負います:
-
- 本人の財産を管理(通帳・不動産など)
- 契約の代理(施設入所、介護サービスなど)
- 家庭裁判所への定期報告(年1回の収支報告など)
業務内容は明確で責任も重いため、事前にしっかりと引き受ける覚悟が必要です。
専門職後見人が選ばれる場合
親族間で後見人をめぐって意見が分かれる場合や、財産管理が複雑な場合には、弁護士や司法書士、行政書士などの「専門職後見人」が選任されることがあります。
本人にとって中立・公平な管理がなされる反面、報酬(管理財産に応じて数万円〜)が発生することも考慮しておきましょう。

まとめ
成年後見制度は、判断能力が低下したご本人を守るための大切な制度です。
しかし、申立てには多くの書類や手続きが必要で、準備と専門知識が求められます。
当事務所では、成年後見申立ての書類作成から裁判所への提出、選任後のフォローまで、一貫した支援を提供しております。
ご家族のサポートが必要な方は、どうぞお気軽にご相談ください。
参照記事等
成年後見はやわかりのウェブサイト「法定後見制度とは(手続の流れ、費用)」
(最終閲覧2025年7月24日)
相続会議のウェブサイト「成年後見人の手続き 申し立てから選任までの流れ、必要書類、費用を解説」
(最終閲覧2025年7月24日)