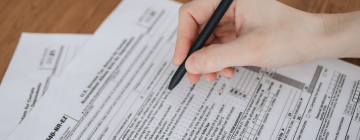遺産分割協議の進め方:トラブルを防ぐための対策
相続が発生すると、遺言書がない場合や遺言書に記載されていない財産については、相続人全員で「遺産分割協議」を行う必要があります。
しかし、この協議がスムーズに進まないと、家族間のトラブルや相続手続きの遅れが生じてしまいます。
本記事では、遺産分割協議の基本的な進め方と、トラブルを防ぐための実践的なポイントを解説します。
遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは、相続人全員が集まり、誰がどの財産を受け取るかを話し合って決める手続きです。
協議が成立したら、「遺産分割協議書」という書面を作成し、全員が署名・押印します。
この協議書がなければ、不動産の名義変更や預貯金の解約など、正式な相続手続きが進められません。
協議を始める前にすべきこと
スムーズな協議のためには、準備がとても重要です。
相続人の確定
-
- 戸籍を収集して、全相続人を確実に把握することが最優先です。
- 異母兄弟や養子など、想定外の相続人が見つかることもあります。
相続財産の調査
-
- 預貯金や不動産、有価証券、借金など、プラスもマイナスも含めて財産を一覧化しましょう。
- 名義が被相続人のままの不動産や、死亡後に支払われる生命保険金なども含めて確認します。
遺産分割協議の進め方(手順)
財産の全体像を共有する
相続人全員が、「どんな財産があるか」を正確に把握できるよう、財産目録を作成して説明します。
これにより、無用な疑念や不信感を防ぐことができます。
分け方の希望を確認する
-
- 不動産を引き継ぎたい人がいるか
- 預金を現金で分けたい人がいるか
- 形見分けなど感情的な希望も考慮します
分割案をたたき台として提示する
-
- 相続人の希望を反映した上で、公平感のある案を提示します。
- 一度で決まらなくても、複数案を用意して話し合う姿勢が大切です。
協議書を作成し、署名・押印
-
- 内容がまとまったら、遺産分割協議書を作成
- 実印を押し、印鑑証明書も添付します
- 不動産登記や預金の名義変更などに使用されます
トラブルを防ぐためのポイント
感情に配慮しつつ冷静に話す
相続には、「お金」だけでなく「親との思い出」や「きょうだい間の感情」が絡みます。
相手の立場や気持ちにも配慮しながら話すことが大切です。
第三者(専門家)を交える
意見がぶつかりそうなときは、行政書士・司法書士・税理士などの中立的な専門家を交えることで、話がスムーズになります。
早めに協議を始める
相続開始後、時間が経つと相続人の状況が変わることもあります(死亡、認知症、連絡不能など)。
なるべく早い段階で協議を開始しましょう。
遺産分割協議がまとまらない場合は?
-
- 家庭裁判所での「遺産分割調停」を申し立てることができます。
- それでも解決しない場合は「審判」で、裁判所が分割内容を決定します。
- 調停や審判になると時間も費用もかかるため、できる限り協議で解決を目指すことが望ましいです。
まとめ
遺産分割協議は、家族の関係性を左右する重要なプロセスです。
「公平に」「冷静に」「丁寧に」進めることが、相続トラブルを防ぐ最善の方法です。
当事務所では、相続人間の対話をサポートしながら、遺産分割協議書の作成や手続き代行まで丁寧に対応いたします。
円満な相続のために、まずはお気軽にご相談ください。
参照記事等
日本公証人連合会のウェブサイト「遺産分割協議」
(最終閲覧2025年7月22日)
三菱UFJ銀行のウェブサイト「遺産分割協議書とは?作成の流れや手続きを解説」
(最終閲覧2025年7月22日)