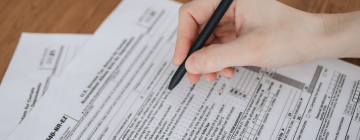認知症になる前にできること:財産管理と信託の選択肢
日本では、65歳以上の約7人に1人が認知症になる時代を迎えています。
認知症を発症すると、自分名義の不動産を売却したり、預金を引き出したりすることが難しくなり、本人も家族も困る場面が増えてしまいます。
では、認知症になる前に何をしておくべきか?
この記事では、認知症に備えた財産管理の方法と、注目される「家族信託」や「任意後見」などの制度について解説します。

認知症になると何が困るのか?
認知症の症状が進むと、次のような制限が生じます。
| できなくなること | 理由 |
| 不動産の売却や活用 | 売買契約などの法律行為に「判断能力」が必要 |
| 銀行口座の管理 | 銀行が取引を停止する場合がある |
| 相続対策や贈与 | 有効な契約が結べない状態とみなされる |
つまり、何も準備をしないまま認知症になると、自分の財産を自由に動かせなくなるのです。
財産管理に備える2つの主な選択肢
認知症になる前に、自分の意思で「もしものとき」に備える制度が2つあります。
任意後見制度
自分が元気なうちに、「判断能力が低下した場合に備えて、誰に後見を頼むか」を契約で決めておく制度です。
-
- 契約締結時:本人に十分な判断能力が必要
- 後見開始時:実際に認知症などになり、家庭裁判所が後見監督人を選任した後に開始
- 対象財産:本人が保有するすべての財産
- 特徴:法定後見よりも柔軟だが、開始までに時間がかかる場合がある
家族信託
信頼できる家族に、自分の財産の管理や処分を任せる契約制度です。
-
- 契約締結時:本人に判断能力が必要
- 開始時:契約締結後すぐに効力が生じる(生前から活用可)
- 対象財産:契約で定めた特定の財産(例:自宅や預金口座)
- 特徴:事前に設計すれば、本人が認知症になっても契約内容通りに管理できる

家族信託の具体例
例:自宅の売却・活用を息子に託す場合
-
- 委託者:本人(父)
- 受託者:長男
- 信託財産:自宅(土地建物)
- 目的:本人の生活資金確保のため、必要に応じて売却できるようにする
- 効果:父が認知症になっても、長男が契約に基づいて売却手続きが可能
任意後見と家族信託の比較表
| 項目 | 任意後見 | 家族信託 |
| 開始のタイミング | 判断能力低下後 | 契約締結直後から |
| 手続き | 家庭裁判所の監督あり | 裁判所の関与なし |
| 対象財産 | 原則すべて | 信託した財産に限定 |
| 管理の柔軟性 | 制限あり(民法の枠組み内) | 自由な設計が可能 |
専門家に相談するメリット
家族信託や任意後見は、制度が複雑であり、個別の事情に応じた設計が必要です。
専門家と相談することで、次のような安心が得られます:
-
- 家族間の役割を明確にできる
- 認知症後の財産凍結を防げる
- 不動産や事業資産の承継対策も同時に検討できる

まとめ
認知症は誰にでも起こりうる現実です。
しかし、「なる前に備える」ことで、財産管理や家族の負担を大きく減らすことが可能です。
-
- 柔軟に管理したい→家族信託
- 広く法的保護を受けたい→任意後見
当事務所では、ご家族の状況や財産の内容に応じて、最適な制度をご提案しています。
元気な今だからこそ、準備を始めましょう。
参照記事等
成年後見はやわかりのウェブサイト「その人らしい暮らしをいっしょにつくる 成年後見制度」
(最終閲覧2025年7月22日)
相続会議のウェブサイト「成年後見人とは? 制度のメリット・デメリット、職務をわかりやすく解説」
(最終閲覧2025年7月22日)