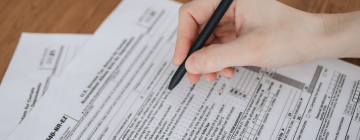家族信託の活用事例:事業承継における信託の活用
中小企業や個人事業主にとって、「誰に・どのように事業を引き継ぐか」は重要な課題です。
特に、後継者が決まっていても、親の認知症リスクや相続発生後のトラブルによって、スムーズな承継が難しくなるケースも少なくありません。
そこで注目されているのが、「家族信託を使った事業承継」です。本記事では、家族信託を活用した事業承継の仕組みと実際の活用例を紹介します。

家族信託とは?
家族信託とは、財産の所有者(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理・運用・処分を任せる契約です。
信託契約により、受託者は指定された目的に沿って財産を扱います。
特徴:
- 委託者が元気なうちに契約する
- 認知症などで判断力が低下しても、財産管理を継続できる
- 柔軟に承継方法を設計できる
事業承継における問題点
事業承継には、以下のようなリスクがあります:
- 経営者が認知症になり、株式や資産の移転ができなくなる
- 複数の相続人間で株式の取り合いが発生する
- 相続手続きが完了するまで、事業の意思決定が滞る
- 生前贈与や遺言だけでは、柔軟な経営引継ぎが難しい
これらの問題は、「経営の空白」や「後継者への不信」につながり、会社の存続に影響を与える可能性があります。

家族信託による事業承継のメリット
家族信託を活用することで、以下のような効果が期待できます。
| メリット | 内容 |
| 認知症リスクへの備え | 親が認知症になっても、受託者である子が資産管理・承継を継続できる |
| 株式の承継管理 | 自社株を信託しておけば、相続トラブルを回避しつつ後継者に経営権を渡せる |
| 柔軟な承継設計 | 「委託者の死亡後は次の人へ」といった二段階・三段階の承継も設計可能 |
| 遺言書より実行力が高い | 信託契約は生前に効力が発生するため、死後の遺言実行よりも迅速かつ確実 |
実際の活用事例:Aさんの会社の場合
背景
Aさんは70歳の製造業社長。後継者は長男Bさん。
自社株の多くを保有するAさんは、認知症への備えと円滑な承継を望んでいました。
信託の設計
- 委託者:Aさん(社長)
- 受託者:Bさん(長男・後継者)
- 受益者:Aさん(存命中)、その後はBさん
- 信託財産:自社株100%
- 目的:経営の継続と財産承継の安定化
結果
- Aさんが認知症を発症しても、Bさんが株式を管理・議決できる体制が構築された
- 遺産分割の対象外となるため、相続時に株式を巡る争いを回避
- 税理士や司法書士と連携し、相続税対策も同時に進められた
家族信託を活用する際の注意点
- 専門家の支援が不可欠(信託契約書の設計には法律・税務・登記の知識が必要)
- 他の制度(遺言、贈与、成年後見)との整合性を検討
- 税務上の取扱いに注意(信託による贈与税・相続税の課税関係)
- 信頼できる受託者の選任が重要

まとめ
家族信託は、経営者が元気なうちに意思を明確にし、事業を次世代へ引き継ぐための有力な手段です。
特に、自社株や不動産などの承継には、信託の柔軟性と実行力が大きな力を発揮します。
当事務所では、事業承継を見据えた家族信託の設計サポートを行っています。
経営者の「想い」と「財産」を次世代へ確実に届けるために、早めのご相談をおすすめします。
参照記事等
税理士法人上原会計事務所のウェブサイト「事業承継対策として家族信託を活用する方法とは?」
(最終閲覧2025年7月8日)
家族信託研究所のウェブサイト「家族信託活用事例E-2:自己信託による自社株の生前贈与で中小企業の円滑な事業承継を試みるケース」
(最終閲覧2025年7月8日)