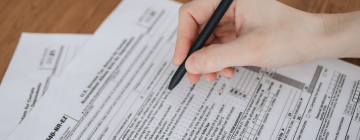相続税対策:基礎控除と節税のポイント
相続が発生すると、相続人には財産の承継だけでなく、相続税の申告と納税という大きな課題も生じます。しかし、適切な対策を行うことで、相続税の負担を軽減することが可能です。本記事では、相続税の基礎控除の仕組みと、代表的な節税対策のポイントについて解説します。

相続税とは?
相続税とは、亡くなった方の財産を相続した人に課される税金です。相続税は相続人ごとに課税され、財産の内容・金額・相続人の人数などによって金額が変わります。
相続税の基礎控除とは?
相続税には、「基礎控除」という非課税枠があり、一定額までは税金がかかりません。
基礎控除の計算式
| 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数) |
たとえば、法定相続人が配偶者と子2人の合計3人であれば、
3,000万円 +(600万円 × 3)= 4,800万円
この場合、相続財産の合計額が4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。

よくある誤解と注意点
「うちは現金が少ないから相続税は無関係」と考える方もいますが、土地・建物・有価証券・生命保険金なども課税対象になります。
また、名義預金や死亡退職金なども注意が必要です。
節税の基本的な考え方
相続税対策は、大きく分けて次の2つの方向から考えます。
財産を減らす(生前贈与)
生前のうちに少しずつ財産を子や孫に贈与することで、将来の相続財産を圧縮できます。
- 年間110万円までの非課税枠を活用する「暦年贈与」
● 教育資金や住宅取得資金の特例贈与を活用する方法も有効です。
評価額を下げる(財産の種類や形を工夫)
同じ1,000万円でも、「現金」と「不動産」では評価方法が異なります。
- 貸家付き土地や賃貸アパートは、相続税評価額が下がる傾向があります。
● 小規模宅地等の特例(自宅や事業用の土地の評価を最大80%減額)も重要です。

相続税の節税に有効な対策例
| 対策内容 | ポイント |
| 生前贈与 | 長期的に計画的に行うのが効果的。非課税枠の範囲で毎年実施。 |
| 不動産活用 | 土地活用により評価額の圧縮+収益化も可能。 |
| 生命保険 | 「500万円 × 法定相続人」の非課税枠がある。納税資金の準備にも。 |
| 家族信託 | 認知症対策と併せて、財産管理を柔軟に行える。 |
専門家に相談するメリット
相続税対策は、個々の家庭状況や財産の種類によって最適解が異なります。
税理士や行政書士、司法書士などの専門家と連携し、早めに対策を立てることが重要です。

まとめ
相続税の課税対象かどうかを確認するには、まず相続財産の把握と基礎控除額の計算が第一歩です。
そのうえで、生前贈与や不動産活用、生命保険の利用など、早めの対策が大きな節税効果を生むことがあります。
当事務所では、相続に関するご相談を初回無料で承っております。
相続税が心配な方は、お気軽にお問い合わせください。
参照記事等
相続会議のウェブサイト「相続税対策9つの方法を厳選 節税のために準備しておくこと 注意点も解説」
(最終閲覧2025年7月8日)
ベンナビ相続のウェブサイト「相続税の節税につながる7つの控除制度と相続税負担を減らす知識まとめ」
(最終閲覧2025年7月8日)