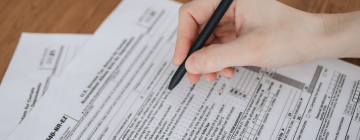就労継続支援B型サービスは、障害をもつ方々が社会参加し、自立した生活を送るために欠かせない制度です。
このサービスは、障害をもつ方が無理なく働き続けられる環境を提供し、自己肯定感を高めるだけでなく、社会的スキルを身につける機会を提供します。
事業所の皆様にとっても、利用者のサポートを通じて社会貢献を果たす重要な役割を担っています。
例えば、あるB型事業所では、軽作業や手工芸を通じて利用者が就労経験を積み、徐々にスキルを向上させています。
また、定期的な評価や支援計画により、利用者一人ひとりに合わせた支援が可能となっています。
このように、就労継続支援B型サービスは、障害をもつ方の社会参加を支え、事業所の社会的価値を高める重要な仕組みです。
この記事では、B型サービスの概要や申請手続き、運営のポイントについて詳しく解説します。
B型事業所から一般就労への移行を成功させるには?
就労継続支援B型事業所(以下、B型事業所)は、一般就労が難しい方に対して、生産活動や就労支援を行う「準備の場」です。
しかし、利用者の中には「できれば将来的に一般企業で働きたい」と希望を持つ方も少なくありません。
本記事では、B型事業所から一般就労への移行を実現するための支援のあり方と成功のポイントを、行政書士の立場からご紹介します。

B型から一般就労への「ステップアップ」は可能か?
結論から言えば、可能です。
ただし、B型は「非雇用型」の支援であり、A型や就労移行支援と比べて一般就労へのルートは明確ではありません。
だからこそ、個別の支援計画と中長期的な目標設定が重要になります。
移行を成功させるためのステップ
ステップ1:就労への意欲と目標を明確にする
- 利用者本人の意欲、生活状況、体調などを丁寧にアセスメント
- 「将来的に何をしたいか」「週何日・何時間働きたいか」といった就労希望の整理がスタート地点です
ステップ2:基礎的な生活・作業スキルの習得
- 毎日の通所・生活リズムの安定
- 報告・連絡・相談、時間管理、清掃などの社会的マナーの習得
ステップ3:段階的に就労体験の機会を設ける
- 企業見学、体験実習、職場体験等を通して「働くこと」のイメージを具体化
- ハローワークや地域若者サポートステーションとの連携も有効です

支援体制の整備がカギ
(1) 個別支援計画に「移行支援」の目標を明記する
- 目標設定→具体的支援内容→評価の流れを記載し、支援記録として蓄積
(2) 就労支援の専門職との連携
- ハローワークの障害者担当、就労移行支援事業所、障害者就業・生活支援センターなどと連携し、スムーズな情報共有と連携支援を行う
(3) 地域企業との関係構築
- 地域の企業に「障害者雇用」の理解を広め、体験実習や短時間雇用の機会を開拓する
移行を実現した成功事例
【事例1】B型から清掃業への移行(30代・男性)
- 通所3年目。生活リズムと作業能力が安定し、清掃会社の職場体験に参加
- 週3日、1日4時間からの雇用開始→1年後に正社員登用へ
- ポイント:「時間を守れる」「集中できる」というB型での経験が評価
【事例2】B型でパソコン作業→事務職へ(20代・女性)
- B型でデータ入力や封入作業を担当
- 地元企業の実習に参加し、能力と態度を認められて採用へ
- 支援者が職場との橋渡し役を担い、スムーズな定着支援につながった
利用者・家族への情報提供と意識づけも重要
就労への移行支援には、利用者本人の意欲に加えて、家族の理解と協力が欠かせません。
- 就労に関する制度(障害者雇用制度、特例子会社、就労定着支援など)について説明
- 「できるところから始める」スタンスで、不安を和らげる支援を行う
移行後の「定着支援」も忘れずに
就職後のミスマッチや人間関係のストレスで離職してしまうケースもあります。
そのためには、以下のようなフォロー体制が重要です。
- 定期的な職場訪問や面談の実施
- 就労定着支援事業所との連携
- トラブル発生時の迅速な対応と仲介

まとめ
B型事業所は「ゴール」ではなく、「スタートライン」です。
すべての利用者が一般就労を目指すわけではありませんが、希望する人が一歩ずつ前進できる環境づくりは、事業所の大切な役割です。
利用者の可能性を信じ、時間をかけて伴走する姿勢が、移行支援の鍵となります。
当事務所では、移行支援に必要な体制整備、加算の取得、就労支援機関との連携アドバイスなどを総合的にサポートしております。
就労継続支援B型サービスは、障害をもつ方の社会参加を支え、事業所が地域社会に貢献できる大切な仕組みです。
このサービスは、利用者が自分のペースで働き、成長を実感できる場を提供し、事業所はその支援を通じて社会的責任を果たすことができます。
また、行政手続きや報酬請求などのサポートを適切に行うことで、事業所の運営を安定させることも可能です。
「ならざき行政書士事務所」では、新規指定申請や指定更新申請、サービス報酬の請求手続きなど、B型事業所の運営に欠かせないサポートを提供しています。
これにより、事業所の皆様は安心して利用者支援に集中することができます。
就労継続支援B型サービスの安定した運営には、確かな支援と適切な手続きが欠かせません。
「ならざき行政書士事務所」は、あなたの事業運営をしっかりとサポートします。
参照記事等
LITALICOワークスのウェブサイト「就労移行支援と就労継続支援の違いとは?」
(最終閲覧2025年7月1日)
Rodinaのウェブサイト「就労移行支援と就労継続支援の違いについて。両方とも利用できないの?」
(最終閲覧2025年7月1日)