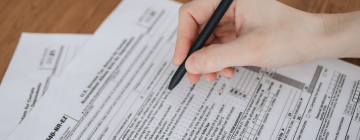就労継続支援B型サービスは、障害をもつ方々が社会参加し、自立した生活を送るために欠かせない制度です。
このサービスは、障害をもつ方が無理なく働き続けられる環境を提供し、自己肯定感を高めるだけでなく、社会的スキルを身につける機会を提供します。
事業所の皆様にとっても、利用者のサポートを通じて社会貢献を果たす重要な役割を担っています。
例えば、あるB型事業所では、軽作業や手工芸を通じて利用者が就労経験を積み、徐々にスキルを向上させています。
また、定期的な評価や支援計画により、利用者一人ひとりに合わせた支援が可能となっています。
このように、就労継続支援B型サービスは、障害をもつ方の社会参加を支え、事業所の社会的価値を高める重要な仕組みです。
この記事では、B型サービスの概要や申請手続き、運営のポイントについて詳しく解説します。
B型事業所でのトラブル対応—よくある課題と解決策
就労継続支援B型事業所(以下、B型事業所)は、障害のある方が働くための場として社会的な意義の高い施設ですが、日々の運営ではさまざまな「トラブル」が発生する可能性があります。
トラブルが長期化すれば、利用者の定着率低下や職員の離職、さらには監査指導での指摘といった重大な影響を及ぼすこともあります。
そこで今回は、B型事業所で起こりやすい課題とその具体的な解決策を紹介します。

利用者間のトラブル
よくあるケース:
- 作業中の小競り合いや言い争い
- 個人の所有物に対する誤解・トラブル
- 「あの人と一緒に作業したくない」といった人間関係の不和
解決策:
- 事前に個別アセスメントを丁寧に行い、相性の良い作業グループを編成する
- トラブル発生時は第三者が冷静に間に入り、感情の背景にある不安や不満を傾聴する
- 繰り返しトラブルを起こす場合は、相談支援専門員や医療機関と連携し、対応方針を検討
無断欠席・遅刻・通所拒否
よくあるケース:
- 前日までは元気に通所していたのに、突然来なくなった
- 慣れてきた頃に急にモチベーションが低下し、継続通所が困難に
解決策:
- 日々の様子を記録し、ちょっとした変化に早期に気づく支援体制を整える
- 無断欠席が続く場合は、家族や相談支援専門員と連携し、状況把握と今後の支援方針を共有
- 「できたことに注目する声かけ」や「選べる作業」など、通所が楽しみになる工夫を日常的に行う

職員と利用者の関係悪化
よくあるケース:
- 支援員の注意や指導がきつく感じられ、利用者が不信感を抱く
- 担当職員との相性が悪く、作業や会話を拒否するようになる
解決策:
- 支援員には障害特性への理解と、適切な言葉づかい・関わり方の研修を行う
- 担当制を固定しすぎず、複数の職員が関わる仕組みをつくることで関係の柔軟性を持たせる
- 苦情や不満が出た場合は、利用者にとって安全な「意見箱」や「中立の相談窓口」を設ける
支援記録や計画書の不備による行政対応リスク
よくあるケース:
- 個別支援計画の見直しが遅れている
- 支援記録の記載内容が曖昧・抽象的
- 実地指導で「運営基準違反」と指摘を受ける
解決策:
- 月1回以上の計画・記録の点検体制をつくる(管理者+別職員のダブルチェック)
- 記録には「いつ・誰が・何を・どのように・結果は?」を意識して具体的に記載
- 実地指導前には、外部の行政書士やコンサルタントに書類整備のチェックを依頼するのも有効

家族との連携不足による支援のずれ
よくあるケース:
- 利用者の通所状況や支援内容について、家族に十分伝わっていない
- 家庭でのトラブルが通所に影響しているのに、事業所が把握していない
解決策:
- 定期的に「家庭との連絡ノート」や「月次報告」などで情報共有を行う
- 面談や個別支援会議の際には、家庭の希望や課題もヒアリングし、連携を深める
- 必要に応じて、相談支援専門員・医療機関と三者連携を組み、支援方針を統一する
トラブル発生時の体制を事前に整えておく
✅ 危機対応マニュアルを作成
- 利用者の暴言・自傷・他害行動などの緊急事態への対処手順を明文化しておく
✅ 職員への対応研修の実施
- トラブル対応に関するロールプレイや研修の実施で、職員の対応力を底上げ
✅ 苦情解決の仕組みを設置
- 苦情受付の窓口を明示し、透明性ある対応体制を整えることで信頼性が高まります

まとめ
B型事業所では、日々の支援の中で小さなトラブルが起こることは決して珍しくありません。
しかし、事前の備えや、発生後の迅速かつ丁寧な対応によって、大きな問題に発展させずに済むケースも多くあります。
トラブル対応の基本は、「情報共有」「傾聴」「連携」です。
事業所全体でこの視点を共有し、職員一人ひとりが安心して支援にあたれる体制を整えていきましょう。
当事務所では、B型事業所の運営における危機管理体制の整備、指導監査対応支援、記録管理体制の構築などをトータルでサポートしております。
事前のチェックや相談も歓迎いたしますので、お気軽にご連絡ください。
就労継続支援B型サービスは、障害をもつ方の社会参加を支え、事業所が地域社会に貢献できる大切な仕組みです。
このサービスは、利用者が自分のペースで働き、成長を実感できる場を提供し、事業所はその支援を通じて社会的責任を果たすことができます。
また、行政手続きや報酬請求などのサポートを適切に行うことで、事業所の運営を安定させることも可能です。
「ならざき行政書士事務所」では、新規指定申請や指定更新申請、サービス報酬の請求手続きなど、B型事業所の運営に欠かせないサポートを提供しています。
これにより、事業所の皆様は安心して利用者支援に集中することができます。
就労継続支援B型サービスの安定した運営には、確かな支援と適切な手続きが欠かせません。
「ならざき行政書士事務所」は、あなたの事業運営をしっかりとサポートします。
参照記事等
B-Searchのウェブサイト「B型事業所でのトラブル例とその対処法について」
(最終閲覧2025年7月1日)
ケイエスガードのウェブサイト「B型事業所でトラブルがあった時はどうする?おかしいと思った時の対処法を解説」
(最終閲覧2025年7月1日)